カテゴリから検索

 | フォトミック、フォトミックAファインダーは指針式で外部からの明かりを取り込んでファインダー内に表示するのだが、暗い場所では当然指針が見えにくくなる。フォトミックイルミネーターは、指針窓を照明するためのアクセサリー。水銀電池1個を使用する。 |
 | フォトミックファインダーを取り外すにはボディ背面のボタンとファインダー側のレバーを押しながら倒して上に引き抜けばよい。ファインダースクリーンはFと互換性がある。 |
 |  |
| 初期型 | 後期型 |
| 一眼レフはミラーの角度が高精度に維持されていなければならない。初期型のほうは一本の金具で保持しているが、後期型になるとY字型の金具に変更されている。理由は不明だが、耐久力を増すためだろうか。 | |
 |  |
| 初期型 | 後期型 |
| 初期型はFのデザインのものに近く、やや不安定で巻き戻しもしづらいものだったが、後期になると肉厚になり操作しやすいように改善されている。デザイン的には初期のもののほうがよい感じがするのだが。 | |

| アイレベルファインダー(DE-1)装着のニコンF2はメーターを必要としないユーザーのために用意されたもの。当然、F2フォトミックよりも軽量である。デザイン的にはFのそれと近いけれど、メーター本体はファインダー内に収めるという思想がFからそのまま踏襲されているわけである。 F2とほぼ同時期に登場したキヤノンF-1は、メーターをボディ内に収めたため、スマートな形になったわけだが、ニコンとキヤノンの設計の方向性が分かれたことになる。F2のアイレベルを基本として、その後にチタンボディも登場するけれど、これもメーターを必要としないプロ用機としての矜持というものであろうか。 メーターは経年変化による狂いや、故障のリスクがあるから、中古市場ではこのF2アイレベルのほうが高価な値付けをされていたりすることが興味深い。他のファインダーとしてはウエストレベルファインダー(DW-1)アクションファインダー(DA-1)高倍率ファインダー(DW-2)などがある。 |
 |  |
| シャッターダイヤル中央にある黒線はシャッターがチャージされている時は水平に、チャージされていない時には7時方向に位置する。Fにも同様の機能があったが、フォトミックファインダーを装着すると見えなくなる。F2独自の機構といってもよい。 | |

| モータードライブMD-2はF2専用。最高5コマ/秒の連写を可能として、フィルム巻き戻しも自動化されている。Fと異なり、無調整互換なので制約はない。ただ、Fと同様にコマ速度によって、使用シャッターに制限がある。Lでは1/4秒以上、M2では1/8秒以上、M2では1/60秒以上、M3とHでは1/125秒以上のシャッタースピードに設定する必要がある。これを守らないと露光中に巻上ってしまうので注意したい。フィルムカウンターは逆算式で、使用フィルムによりコマ数を設定する必要がある。裏蓋はMD-2専用の「カメラバックMF-3」。フィルムの自動巻き戻しを自動停止することが可能。またフィルムのリーダー部を残すことができる。自動現像機に入れる際の手間を省くためだと思うが、反面、露光したフィルムを再装填してしまう事故が起こる可能性があるから注意する必要がある。 |


| カメラの発展は自動化と同義であり、F2が登場した当時は露出の自動化(AE)をいかに実現するかがメーカー共通の目標だったように思う。 フルメカニカルカメラであるF2とAEはそぐわないと思うのだけれど、F2フォトミックSとSBにはEEコントロールユニットDS-1とDS-2が、フォトミックASにはDS-12が用意されサーボモーターコントロールによるシャッター速度優先AEを可能とした。 もっともAEといえど、設定した任意のシャッター速度に対してモーターのチカラを使って適正露出値まで絞り環を回してしまえというシロモノなのである。言い換えれば指で絞り環を回すかわりにモーター動力を使用したのだ。おそらく無人撮影などに使用されたのではないかと推測される。 写真のF2フォトミックASとEEコントロールユニットDS-12は発展型ではあるものの動作は同じ。ただし、フォトミックSファインダーの受光素子は応答速度の遅いCdsだったのに対して、ASではSPDとなり、応答速度は飛躍的に向上した。 |
 |  |
| DS-12の動作ボタン。押すと電源がオンになる。ダイヤルの位置によっては常時測光が可能なようにもできるが電池消耗が大きいようだ。 | 巻き戻しクランクを持ち上げて、ストロボ用のシューにカップリングさせる方式。固定するのはカメラ前面のシンクロターミナルのネジを使用するため、前面には独自のターミナルが新たに設けられている。 |
 |
| EEコントロールユニット動作 |
| ニコンF2 モータードライブ装着時のフィルム巻き戻し動作 |
| 赤城耕一 ニコンFとF2のシャッター音について語る。 みなさんは、FとF2のシャッターの響き方について、違いがわかりますでしょうか? 音量を大きくするか、ヘッドホンで聞くとわかり易いです。 |
 | 赤城耕一 東京生まれ。出版社を経てフリー。エディトリアルやコマーシャルの撮影のかたわら、カメラ雑誌ではメカニズム記事や撮影ハウツー記事を執筆。戦前のライカから、最新のデジタルカメラまで節操なく使い続けている。 主な著書に「使うM型ライカ」(双葉社)「定番カメラの名品レンズ」(小学館)「ドイツカメラへの旅」(東京書籍)「銀塩カメラ辞典」(平凡社) ブログ:赤城耕一写真日録 |
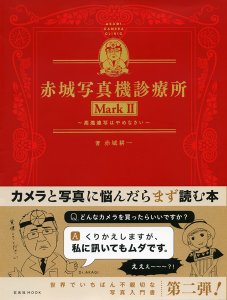 | 「赤城写真機診療所 MarkII」 〜高速連写はやめなさい〜 著者 赤城耕一 価格:1,900円+税 電子書籍版:1800円+税 <紙版> Amazon ヨドバシカメラ.com 紀伊國屋書店 <電子版> Amazon Kindleストア |
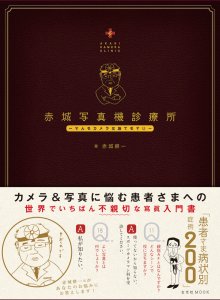 | 「赤城写真機診療所」 〜そんなカメラは捨てなさい〜 著者 赤城耕一 価格:1,800円+税 電子書籍版:1700円+税 <紙版> ヨドバシカメラ.com 紀伊國屋書店 <電子版> Amazon Kindleストア |
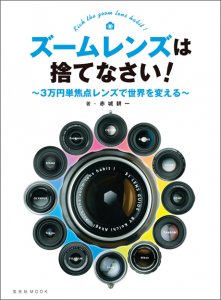 | 「ズームレンズは捨てなさい!」 著者 赤城耕一 価格:1,800円+税 電子書籍版:1500円+税 <紙版> 完売・絶版 <電子書籍> Amazon Kindleストア ヨドバシカメラ.com |