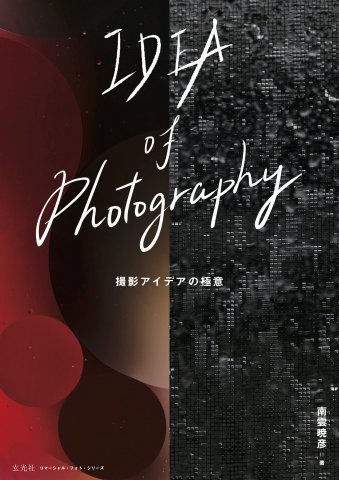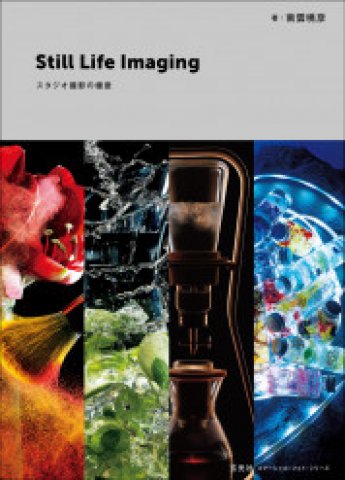南雲暁彦のThe Lensgraphy
公開日:2022/03/23
Vol.4 Ernst Leitz Summarit 5cm F1.5「雨天決行」
南雲暁彦
 このレンズをつけていたら「ズマリットですか」と声をかけられた、有名なレンズである。シュナイダー社のクセノン5cm F1.5から技術提供を受けて作られたと言われるライツ社初の大口径レンズで焦点距離を5cmと表記するが、まあ50mmということだ。現行のズマリット50mmはF2.4と50mmでは一番暗いレンズだが、このズマリット5cmは大口径ハイスピードの元祖であり、この後ライカはズミルックスF1.4/50mmを生み出す事となる。
このレンズをつけていたら「ズマリットですか」と声をかけられた、有名なレンズである。シュナイダー社のクセノン5cm F1.5から技術提供を受けて作られたと言われるライツ社初の大口径レンズで焦点距離を5cmと表記するが、まあ50mmということだ。現行のズマリット50mmはF2.4と50mmでは一番暗いレンズだが、このズマリット5cmは大口径ハイスピードの元祖であり、この後ライカはズミルックスF1.4/50mmを生み出す事となる。
クセ玉として有名で、「ハイスピード」「ぐるぐるボケ」「虹ゴースト」というわかりやすい必殺技を持っているのでオールドレンズをわかりやすく楽しめる。どこからどう見ても金属とガラスの塊というルックスも素晴らしいと思ったし、M10-Pにつけたときのバランスもとても好い、このよくメンテナンスされた個体は操作性もスムースで使っていて楽しめた。
さて、まずはこの必殺技を僕の好きな夜景で試してみようと思い、夜の街に出かけた。
 Ernst Leitz Summarit 5cm F1.5(以下、同)
Ernst Leitz Summarit 5cm F1.5(以下、同)
1/60秒 F1.5 ISO640 F1.5の開放値はズームレンズ全盛の今となってまた輝く。柔らかい光をたっぷりと取り込みシャッタースピードを稼ぐ、ハイスピード健在だ。 1/60秒 F1.5 ISO640夜景の点光源でぐるぐるボケのフォルムを浮き彫りにする。じっくりご覧になりたい方は是非とも拡大してみて欲しい。作画としてはあまり派手にぐるぐるさせず、このぐらいの使い方が僕としては好みかな。街の雰囲気を素敵に彩ってくれる。
1/60秒 F1.5 ISO640夜景の点光源でぐるぐるボケのフォルムを浮き彫りにする。じっくりご覧になりたい方は是非とも拡大してみて欲しい。作画としてはあまり派手にぐるぐるさせず、このぐらいの使い方が僕としては好みかな。街の雰囲気を素敵に彩ってくれる。 1/60秒 F1.5 ISO2000スペシウム光線に匹敵する必殺技、虹ゴースト。まるで月光が作り出したように演出してみた。これを撮っていて本物のルナレインボーをイグアスで撮影したときのことを思い出すという想像もつかなかった事が起きた。日本ではこうやってルナレインボーを作ればよいのだ(笑)。しかし、なんという破壊力。
1/60秒 F1.5 ISO2000スペシウム光線に匹敵する必殺技、虹ゴースト。まるで月光が作り出したように演出してみた。これを撮っていて本物のルナレインボーをイグアスで撮影したときのことを思い出すという想像もつかなかった事が起きた。日本ではこうやってルナレインボーを作ればよいのだ(笑)。しかし、なんという破壊力。 このレンズを手にしたら必ずやらなくてはならないのがレンズを覗き込んで絞りを動かすことだ。僕がこのレンズを見て最も驚いたのがこの絞り羽の枚数とその動き。なんと15枚もの絞り羽が使われ、ガンメタに鈍く光っている、これは無条件にかっこいい。この15枚の絞り羽が円形を保ったまま稼働する様を見て、正直それだけで惚れてしまった。007も真っ青である。
このレンズを手にしたら必ずやらなくてはならないのがレンズを覗き込んで絞りを動かすことだ。僕がこのレンズを見て最も驚いたのがこの絞り羽の枚数とその動き。なんと15枚もの絞り羽が使われ、ガンメタに鈍く光っている、これは無条件にかっこいい。この15枚の絞り羽が円形を保ったまま稼働する様を見て、正直それだけで惚れてしまった。007も真っ青である。
さて、実はここからがメインディッシュである。
このレンズはぐるぐるボケや虹ゴーストを出すために生まれてきたわけではないはずで、今となっては必殺技となったその癖を使わずして素直に撮影をしてみたいと思った。フラットな光と時間の中で、時を超えてきたレンズを使い僕の時間を撮影する。
久しぶりに連絡した友人と芝浦アンカレッジで待ち合わせし、雨のレインボーブリッジ遊歩道に向かった。
このレンズはMマウントを装備していたので1954年のライカM3登場に合わせて作られた後期型、ズミルックスF1.4/50mmが登場する1959年までの間に製造された物だろう。1970年製の筆者より長い年月を乗り越えて今手元にある。いったい何人のフォトグラファーの光を取り込んできたのだろう、2022年、僕もその光の年表に時を刻むことにしよう。 1/250秒 F1.5 ISO100「雨天決行」
1/250秒 F1.5 ISO100「雨天決行」
できれば曇りぐらいがいいかなあと思っていたが、天気予報は曇りのち雨。それでも日程を変えなかったのはどんな天気でもこの場所の雰囲気は好きだったし、少し重たい空気やフラットな光の方がズマリットに合っているような気がしていたからだ。雨だって何かの役に立つだろう。
 1/750秒 F1.5 ISO200「久しぶり、雨だね」から少し話をして歩き始める。色々な背景のアングルでシャッターを切って行くが、この空気に馴染んできて撮影用の表情が消えた時からが本当の始まりだ。レインボーブリッジの遊歩道から鉄格子がなくなり広い東京を望む場所に来ると視線が自由になった、その場にいることの違和感が消えて今の時代の景色になって行く。
1/750秒 F1.5 ISO200「久しぶり、雨だね」から少し話をして歩き始める。色々な背景のアングルでシャッターを切って行くが、この空気に馴染んできて撮影用の表情が消えた時からが本当の始まりだ。レインボーブリッジの遊歩道から鉄格子がなくなり広い東京を望む場所に来ると視線が自由になった、その場にいることの違和感が消えて今の時代の景色になって行く。 1/350秒 F1.5 ISO200
1/350秒 F1.5 ISO200 1/500秒 F1.5 ISO200時折撮影した写真を見せると、「へー、こんなふうになるんだ。面白い」と言う。絞りはほとんど開放で撮っているので柔らかい空気の中に入り込んだような写真が出来上がり、スマホの写真とは違う事に敏感に反応してくれる。露出計を振り切るぐらい明るく撮ってこのトーンを出した。ピーカンじゃ無理だな、やはり天気も味方してくれている。
1/500秒 F1.5 ISO200時折撮影した写真を見せると、「へー、こんなふうになるんだ。面白い」と言う。絞りはほとんど開放で撮っているので柔らかい空気の中に入り込んだような写真が出来上がり、スマホの写真とは違う事に敏感に反応してくれる。露出計を振り切るぐらい明るく撮ってこのトーンを出した。ピーカンじゃ無理だな、やはり天気も味方してくれている。 1/90秒 F1.5 ISO200
1/90秒 F1.5 ISO200
1/180秒 F1.5 ISO200この5cmレンズの最短撮影距は3.5フィート、よりちょっと手前までフォーカスリングは動き、まあ大体1mぐらいといったところだ。一般的には85mmがポートレートレンズの代表だが、5cmのこのぐらいの距離感の方が僕は好きかもしれない。85mmのような大きなボケにはならないので、ズマリットF1.5開放のごく柔らかい描写はシチュエーションを残したまま背景と人を完全に一体化し、その柔らかい世界の中で存在や温度を取り込んでいく。僕の大好きなズミクロンでもこうはいかないかもしれない、必殺技を使わなくてもズマリットは素晴らしいレンズ、それにマスク越しに声を届かせるには85mmじゃあ遠いなと感じた。
人の出会いも、レンズとの出会いも、天気も、色々な偶然でこの瞬間が生まれて行く。流れて行く時間は決して止まる事はない、その移ろいを止めてしまう写真というものは人がその瞬間の、自分の存在や意識、感情を残しておきたいという気持ちの産物であり、その瞬間は二度と訪れないという残酷さも秘めている。
それでも人は写真を撮り続け、そこに芸術性まで見出してきた。
撮影をしながらレインボーブリッジの遊歩道を渡りきって、お台場側の砂浜に降りた。そこで彼女はこっち側からみる事はあまりないからと目の前の風景にスマホのシャッターを切っていく。僕にはそれがすごく印象的だった。 1/180秒 F1.5 ISO200
1/180秒 F1.5 ISO200 1/125秒 F1.5 ISO200その時空から音を取り去り、匂いを取り去り、色を取り去り、時間で切り取った物がモノクロの写真である。これ以上何かを取ってしまうとリアリティーは減少して行くが、逆にこれ以上ないほどの現実としての証明に使われてきた。
1/125秒 F1.5 ISO200その時空から音を取り去り、匂いを取り去り、色を取り去り、時間で切り取った物がモノクロの写真である。これ以上何かを取ってしまうとリアリティーは減少して行くが、逆にこれ以上ないほどの現実としての証明に使われてきた。
つまり時間(=時代)と形(現象)ということについて最も裸の状態で、見るものにストレートに事実が伝わって行く、それがモノクロ写真の強さであり、魅力となっている。
そんなフィルムのモノクロ写真全盛に生まれたこのズマリットは、僕のこの時間もモノクロで残したい瞬間を作らせた、面白いレンズだ。
雨が強くなってきてズマリットを濡らすわけにもいかないので、一度撮影を切り上げて芝浦に戻ることにした。 1/350秒 F1.5 ISO200
1/350秒 F1.5 ISO200 1/90秒 F1.5 ISO1000
1/90秒 F1.5 ISO1000
1/60秒 F1.5 ISO3200 1/60秒 F2.8 ISO5000
1/60秒 F2.8 ISO5000 1/60秒 F1.5 ISO1600 面白い撮影だった、新製品の撮影はいくらでもやってきたが自分より年季の入ったレンズとここまでしっかり付き合ったのは初めてだったかもしれない。オールドレンズの楽しさはボケ味やゴーストなど物理的な特徴を活かすことだけではなく、時間の長さや流れ、その中で今自分は何を刻んでいくのかを感じられる事だと思った。意味があるとか価値があるとかそういう立派な話ではなくて、流れて行く時間の中で今ここにいる事実が残ること、それを再認識したのだと思う。
1/60秒 F1.5 ISO1600 面白い撮影だった、新製品の撮影はいくらでもやってきたが自分より年季の入ったレンズとここまでしっかり付き合ったのは初めてだったかもしれない。オールドレンズの楽しさはボケ味やゴーストなど物理的な特徴を活かすことだけではなく、時間の長さや流れ、その中で今自分は何を刻んでいくのかを感じられる事だと思った。意味があるとか価値があるとかそういう立派な話ではなくて、流れて行く時間の中で今ここにいる事実が残ること、それを再認識したのだと思う。 1/90秒 F1.5 ISO2500 オールドレンズに負けず、写真も長く残せたら良いと素直に思う。残したいと思う写真を撮りたい、それがフォトグラファー共通の想いだろう。やはりそれはどう生きるか、ということだ。
1/90秒 F1.5 ISO2500 オールドレンズに負けず、写真も長く残せたら良いと素直に思う。残したいと思う写真を撮りたい、それがフォトグラファー共通の想いだろう。やはりそれはどう生きるか、ということだ。
エピローグ
もう少しだけ、このレンズの事。 
RIMOWAクラシックフライトの背景がよく似合う。クールでノーブルな佇まいのレンズだ。
見た目はシルバーボディとの相性がいいと言われるが、ブラックボディと合わせてもなかなか良い。黒を受けたメタル外装がよりズマリットの立体感を際立たせるのだ。 1/90秒 F1.5 ISO100絞ればシャープとよく言われているが、絞り開放でも条件によってはキレを見せると言っておこう
1/90秒 F1.5 ISO100絞ればシャープとよく言われているが、絞り開放でも条件によってはキレを見せると言っておこう
オールマイティーではないが、ずっとつけておいてもいいなと思わせる使いやすいレンズだった。モデル:Aska
コンテンツ記事関連商品ライカ
レンズ交換式
¥1,530,000
カメラのキタムラ
Leica (ライカ)
デジタルカメラ
¥1,333,000
マップカメラ
Barnack
レンジファインダー用
¥68,000
レモン社
Leica (ライカ)
デジタルカメラ
¥930,800
マップカメラ
Leica (ライカ)
デジタルカメラ
¥1,035,800
マップカメラ




















 1/90秒 F1.5 ISO100
1/90秒 F1.5 ISO100